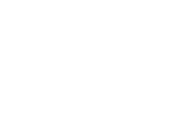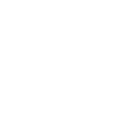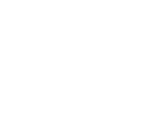Vol.1
プロジェクト誕生の背景にあった想いと行動
2023.06.30

―――このプロジェクトがどのように発足したのか、まずは経緯を教えてください。
片岡
そもそもポーラは創業から90年以上、女性を応援してきた歴史があります。化粧品はもちろん、40年以上前から健康食品を提案したり、ライフケアアイテムを発売したりといったプロダクトでのサポートがひとつ。もうひとつは、仕事を持つことによる女性の自立=経済的な意味でのサポートです。そんななか、ここ数年、社員のあいだで自分の業務以外に、さまざまな活動を通して自発的にフェムケアに取り組む人が増えてきたんです。その一例が、今日参加している馬庭さんや馬場さんの活動です。
そもそもポーラは創業から90年以上、女性を応援してきた歴史があります。化粧品はもちろん、40年以上前から健康食品を提案したり、ライフケアアイテムを発売したりといったプロダクトでのサポートがひとつ。もうひとつは、仕事を持つことによる女性の自立=経済的な意味でのサポートです。そんななか、ここ数年、社員のあいだで自分の業務以外に、さまざまな活動を通して自発的にフェムケアに取り組む人が増えてきたんです。その一例が、今日参加している馬庭さんや馬場さんの活動です。
-

-
馬庭
私は2019年に新卒で入社したのですが、重い生理痛の時などは「社会人って大変だなぁ」「でもまあ、我慢するしかないな」と諦めて仕事をしていました。でもちょうどその頃、フェムテックという言葉が巷で流行りだしまして。ポーラはそうは謳ってはいなくてもフェムケアをしてきた会社なんですが、生理や更年期については、まだまだできることがあるのでは?考え始めたんです。
そこで、自分のSNSで友人に生理に関するアンケートをとり、自分なりに課題を整理。2021年の社内のビジネスアイデアコンテストに「女性の健康をテーマにした新規事業」でエントリーしました。すると審査を通過して「一緒にプロジェクトを進めるメンバーを集めなさい」という流れに。当時入社3年目の私は、まずは信頼できて知見の広い先輩を…と思い頼ったのが館野さん、そしてもう3人のメンバーでした。
-

-
館野
実は私はその頃、フェムケアという言葉すら知らなくて。でも馬庭さんの話で、こんなに苦しんだり困ったりしている人がいるんだということを初めて知り、「これは『大ごとだ!』」くらいの気持ちになったのを覚えています。
私は、ポーラの創業理念である「一人ひとりに寄り添う」に共感して入社したので、仕事でもプライベートでも、大切な人や目の前で助けを求めている人には、できる限り力になりたいと思っているんです。
馬庭さんの仕事のスタイルには学ぶことが多く、特に自分の想いを強く伝播させる力にいつも感心しています。ありたい姿ややりたいこともわかりやすく、馬庭さんとなら必ず実現できるプロジェクトだと確信しました。兼任プロジェクトで忙しくなるのは明白でしたが、即答で「一緒にやりたい!」と言いました。断る理由がなかったですね。
馬庭
その後、約100名にヒアリングやアンケートを実施し、さまざまな調査や検討を経て辿り着いたのが、「タブーを自由にラボ」という、ポーラ主催の異業種合同参加型プロジェクト。まずはこちらを月1回、計5回開催する運びとなりました。これについてはのちほど詳しくお話します。
馬庭
その後、約100名にヒアリングやアンケートを実施し、さまざまな調査や検討を経て辿り着いたのが、「タブーを自由にラボ」という、ポーラ主催の異業種合同参加型プロジェクト。まずはこちらを月1回、計5回開催する運びとなりました。これについてはのちほど詳しくお話します。
-

-
馬場
2人のお話を聞いてふと思い出したんですが、私の活動も、馬庭さんの影響を受けた部分があるなって。彼女がコンテストに応募する頃、同じ部署にいたんですが、一緒にランチをした時に「女性の健康支援をしたい」っていう話を聞いて、すごくいいなぁと思ったんです。馬庭さん世代が生理の問題だったら、私は更年期の問題に取り組めるんじゃないかって。
実は私、40代後半で高齢出産をしまして。
産休と育休を経て仕事に復帰したら、その途端に更年期症状が出てきたんです。職場では相談できないし、イライラするし(笑)。そんな感じで一人で悩んでいた時に、仕事仲間と「私も同じよ」って語り合う機会があり、すごくホッとしたんです。私が必要としていたのは、語り合う場だったんだ!と。そこで、有志3人で交流会を立ち上げて「クラブアマゾネス」と命名。最初はランチタイムのオンライン交流会、次第に更年期の正しい知識を得ることも必要だと感じ、婦人科の先生の講義をウェビナーで開催するなどしてきました。今ではメンバーも増え、社内の認知も広がっています。
片岡
3人の活動の他にも、静岡エリアのスタッフが行政と協力して生理用品の支援をしていたり、有志が産休・育休のコミュニティを立ち上げていたりと、ふと気づくと数多くの取り組みが社内で生まれていました。だったらこれを会社としてひとつにまとめて、社内にも社外にも発信し、大きなうねりにしていこう。そう考えて生まれたのがこのプロジェクトであり、今回のフェムケア宣言です。企業のトップダウンの施策ではなく、実体験や課題を感じた社員の小さな声や活動が集まって会社が動いたという事実は、わたしたちにとって大きな誇りでもあるんです。
Vol.2に続く
片岡
3人の活動の他にも、静岡エリアのスタッフが行政と協力して生理用品の支援をしていたり、有志が産休・育休のコミュニティを立ち上げていたりと、ふと気づくと数多くの取り組みが社内で生まれていました。だったらこれを会社としてひとつにまとめて、社内にも社外にも発信し、大きなうねりにしていこう。そう考えて生まれたのがこのプロジェクトであり、今回のフェムケア宣言です。企業のトップダウンの施策ではなく、実体験や課題を感じた社員の小さな声や活動が集まって会社が動いたという事実は、わたしたちにとって大きな誇りでもあるんです。
Vol.2に続く